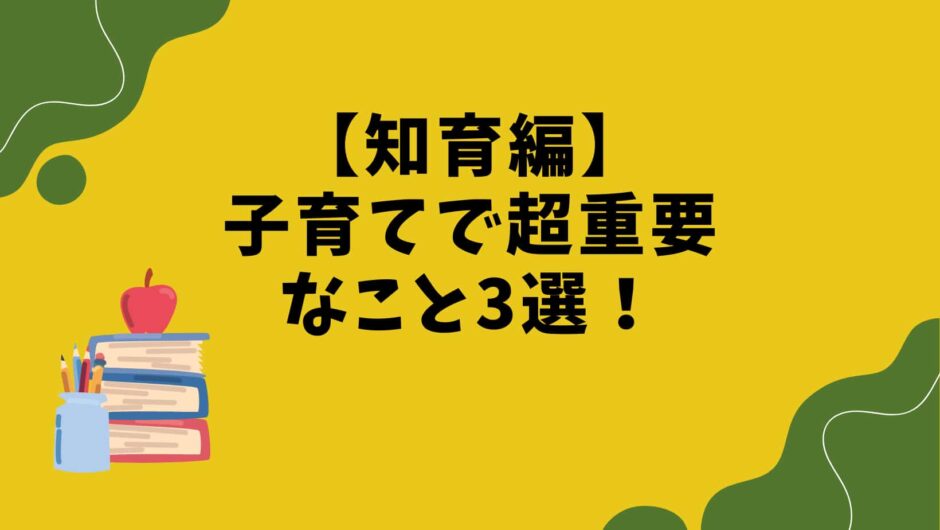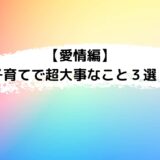僕は全然頭がよくなかったから、子どもにはせめて勉強ができるようになってほしいな

自分ができなくて困ったことは子どもにはできるようになってほしいよね

勉強はもちろんできてほしいけど、それだけじゃなくていろんなことを自分で考えられる人になってほしい!
でも自分にはできないからどうやって子育てしていけばいいかわからないよ!

子どもに教えたいと思ってもなかなか難しいこともあるよね
今日は子どもの知能の伸ばし方について見てみよう
- 子育てを真剣に頑張っているけど、何を頑張ればいいのかわからない方
- これから子育てをする新パパ新ママ
- いろいろ勉強したけど、結局どうやればいいかわからなかった方

子どもの知育で最も効果が高いものが「絵本」です。絵本は図書館に行けば無料で何冊も借りることができます。種類も数えきれないほど、読み切れないほどたくさんありますので数に困ることはありません。さらに、一冊一冊がプロが「子どもに伝えたいこと」を載せてありますので、自分で伝えたい事を考える必要もありません。
時々絵本の後ろに作者のメッセージが書かれています。それを読むことで「この絵本はこういうことを伝えてくれているのか」と驚かされます。難しい内容をいかに「子どもでもわかるように簡単にかみ砕けるか」を真剣に考えてくれた作者の熱意が伝わります。
絵本には今までの人類の知識や作者の熱意が詰まっているのでこれを利用しない手はありません。どんどん読んでいきましょう!(‘ω’)ノ
図書カードは人数分作れますので、夫婦と子どもで3枚カードを作ることができます。1枚で10冊程度借りられますので、最大30冊も借りることができます。2週間ごとにこれだけの本を読むのは大変ですが、上限をあまり気にしなくていいというのはストレスを感じずにすみます。
ちょっとしたことですが、図書館では絵本は作者の名前順で並んでいます。絵本はタイトルで覚えることが多いと思いますが、それだと図書館で探しにくいので、気に入った絵本がありましたらタイトルではなく作者で覚えておくと色々便利です。
具体的には、日本語(言語)の能力と道徳や倫理観を楽しく勉強することができます。
読む絵本が本当に多種多様で読む本によっても変わってくるのですが、友達との助け合いや、傷つけたりすると相手が痛い思いをすること、悪いことをすると自分に罰が当たるといったことなどを考えるきっかけになります。日常生活で困ったときにどうするかを考えるきっかけになりますので、困ったときの問題解決能力も身につけられます。
特に、日本語の能力は非常に重要です。最近は早期の英語学習を!という話をよく聞きますが、たくさんの言語を話せる人に聞いてみると、口をそろえて「日本語が一番難しい」と言います。その難しい日本語を習得しなければならないので、僕はむしろ日本語の能力を優先的に伸ばす必要があると考えています。
少し硬くなりましたが、要するに定期的に(できれば毎日)絵本を読む習慣をつけましょう。みなさんもさんざん言われてきたことだとは思いますが、本当に大事で本当に楽しいです。最初は嫌がっても続けていると子どもも喜んでくれるようになりますので、ぜひ続けてください。
僕は妊娠中から絵本を読み始めていました。そして出産して2歳くらいまでは読んでも絵本を見ずに違う遊びをしていて「聞いてるのかな?」と不安に思いながら読んでいました。するとある日絵本を持ってきて「これ読んで」と言ってきたのを覚えています。もちろんはっきり喋れたわけではありませんでしたが気持ちは伝わりました。
聞いていないように見えても意外としっかり聞いていたようで安心しました。
絵本の読み方についても色々ありますので↓こちらの記事↓を参考にしてみてください。
僕は毎日子どもが寝る前に読むようにしていました。寝る時の習慣にすることによって毎日読みやすかったのと、寝る前のことは記憶に残りやすく絵本の効果をより効率よく定着できると考えたからです。
続けていると、寝る前には子どもが自分で絵本を用意して「これは今日読んでこれは明日読む」と言って予定を立てるようになってきました。寝る前でしたがちょっと感動しちゃいました。
最後におすすめの絵本をいくつか紹介しておきます。絵本は多読が基本ですのでいい絵本を探そうと思う必要はないですが、超定番くらいは読んでおいてもいいかもしれません。本当はもっと載せたいですし写真もつけたいのですが、いろいろありまして割愛させていただきます。
【0歳におススメ】
かがくいひろし 作 「だるまさんシリーズ」(全3冊)
リズミカルで読んでいて楽しいですし、そういう発想もあるんだ!と読んでいるパパママも一緒に楽しめる作品です。また、親戚の出産祝いや1歳の誕生日プレゼントなどにもおすすめです。
【2歳におススメ】
林明子 作 「おつきさまこんばんは」
カンタンですが時間の流れを感じられる作品になっていて、初めてのストーリー絵本としてもおすすめです。嬉しい、悲しいというおつきさまの感情が読み取れます。うちの子もすごく気に入っている絵本です。
【4歳におススメ】
いもとようこ 作 「かぜのでんわ」
4歳になるとちょっと長い絵本も読めるようになりますね。かぜのでんわは少し重い内容で4歳にはまだわからないかもしれませんが、今のうちの読んでおくことで将来何かあった時に「そういうことだったんだ」と思い出してくれるかもしれません。
ちゃんと伝わったときには本当にうるっとしてしまう内容です。うちの子はどうかわかりませんが、何となくわかっているような気がします。そして本当にお気に入りで、毎日のように「かぜのでんわ読んで」と言ってくれます。

積み木は最強の知育おもちゃです。
積み木で遊ぶことによって、空間認知能力(立体感)を鍛えることができますし、積み木で何作ろうかなと考えることでデザインセンスや空想世界の想像や実際に作るためにどうやって積み上げていけばいいかという計画性や問題解決能力が身につきます。
子どもにとってはただ遊んでいるだけなのですが、それだけでたくさんの能力を身につけています。
また、積み木を置いた時の高さの違いに気づいたり、これは傾いていて上に乗せられないことがわかったり、どうすれば高さをそろえられるかを考えたりできます。この高さをそろえるというのは小学校の比の計算などに役立ちます。また、積み木を何個乗せたかを考えますのでそのまま算数の能力を高めることにつながります。
このように積み木にはたくさんのメリットがありますので、少しでもいいので最低限積み木は買っておきましょう。
選び方ですが、いきなり突飛なものを選びたくなる気持ちをぐっとこらえて、最初は色のないオーソドックスな積み木にしましょう。何もないものの方が想像の幅が広がります。しばらくしてから色がついたものやちょっと変わったものを追加してもいいかもしれません。
また、どんどん遊んでいくにつれてちょっと物足りないと感じることもあると思います。そういった時は、できるだけ今使っているものと高さが揃うものを選ぶことで、今まで使っていたものをそのまま拡張することができます。
高さが違うとどうしても上と横に広げていくのが難しいです。同じ高さがない場合は、ちょうど半分(2倍)やちょうど3分の一(3倍)の高sのものを選ぶといいです。こうすることで「この積み木1個とこの積み木3個で同じ高さになる」ということを直感的に分かるようになります。
こうやって今後の増やし方も考えて計画的に積み木を買っていけるといいですね(*’ω’*)
0歳や1歳のころは、僕が積み上げて子どもが壊すという遊びをよくやっていました。壊すのはカンタンで楽しいですし、これを続けると積み木に興味を持ってくれるようになりました。
うまく積み上げられなくてイライラして泣くこともありますが、続けているうちにできるようになっていったので、その過程をほめていくとさらに積み木で遊ぶようになりました。
倒れないように慎重に真剣に積み上げていく姿を見るとちょっとうるっとしちゃいます。
他にも、折り紙や工作など指と頭を使う遊びもおすすめです。

子育てをしているとわかりますが、公園はめちゃくちゃいい場所です。
子どもは思い切り体を動かすことができますし、パパ友ママ友との交流の場にもなります。
特に日光を浴びて遊ぶことで朝と昼と夕方の違いを知ることができ、時間の流れを感じることができます。日光には体内時計を調整する働きもあり、子どもの自律神経を整えてくれます。
また、思い切り体を動かすというのは家ではなかなかできないことですので、子どもにとってもストレス発散の場になるでしょう。公園で遊ぶことによって自然と体力がつきますし、「土の感じ」や「高いと怖い」という感情など外でしか経験できないことをたくさん経験できます。また季節の変化を感じられることも魅力ですね。
また、植物や花、天気などにも興味を持てるかもしれません。もしも新しい発見があって興味を持てたのであればそれに関する絵本や図鑑を借りてきて一緒に読めるとより楽しくより知識を深めていけます。公園には発見がいっぱいありますので、子どもも興味を持って自発的に遊べます。
他の知らない子どもたちも一緒に遊んでいるので、遊具の順番を守ったり、持ってきたお砂場セットを貸し借りしたりと子ども同士の交流もできます。特に幼稚園では出来ない、小学生やおじいさんおばあさんなど年齢の離れたひととの交流ができるのも魅力です。ちょっと挨拶をするだけでも違いを知るという経験はお互いにとっていい刺激になり価値があります。
知育や勉強は机に向かって集中するというイメージを持っている方も多いと思いますが、子どものうちはなかなか難しいので無理にやらせても効果が薄いです。むしろ勉強を嫌いになって後々勉強したくなくなってしまうことの方が問題です。小学校に入るまではおもちゃ(教具)で遊ぶというのをメインにした方が今後も伸びていきやすいです。
具体的にやること
①定期的に図書館に行き絵本を借りてくる。そして毎日読む
絵本は言語能力や倫理観、生活スキルを学べる
②透明の収納ケースと積み木を買い、部屋に置いておく
積み木は空間認知能力や算数を学べる
③曜日や時間を決めて公園に行く
公園は体力や自然を学べる

あれこれ難しく考えても実行できなきゃ意味ないね
これだけシンプルにしてくれると僕にもできそうだな

本を読んで「こういうのがいいよ!」と言われても、自分で考える時間がなかったり、自分で考えたことがあっているのか分からなかったり、不安になって実行に移せないことも多いよね。

僕は、さっそく図書カードを作ってこようかな。

いいね!
絵本を無料でたくさん借りられるという破格のサービスを利用しない手はないね!
お子様も元気に育ってくれるといいね!
↓関連記事はこちら↓